

|


 |
今でも江戸文化の香りが漂う町、川越。
蔵造りの店が並び、歴史の流れを感じさせるその街並みに、天明3年(1783)の創業時を偲ばせる佇まいの店構えをみせているのが銘菓・亀屋の本店である。代々川越藩の御用達を勤めた老舗だ。その200年に及ぶ伝統と、代々の当主による時代に合わせた革新の見事な融合が、店頭に並ぶ一品一品に息づいている。
8代目となる現当主・山崎嘉正社長に、和菓子のルーツから今後の展望までお話を伺った。 |
|

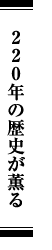 ― 銘菓・亀屋本店 ― 古くは川越藩17万石の城下町として栄え、今でも江戸文化の香りが漂う 「小江戸」川越。 ― 銘菓・亀屋本店 ― 古くは川越藩17万石の城下町として栄え、今でも江戸文化の香りが漂う 「小江戸」川越。
中でも人気の蔵造りの街並みに、創業時の佇まいを彷彿とさせる土蔵造りの店構えを見せているのが、亀屋の本店である。 年間400万人が訪れる川越市の一番街にあり、観光客の足も途絶えることがない。
「わたしども亀屋の創業は天明3年(1783)、初代・山崎嘉七が今の場所で商売をしたという記録が残っています」
そう語ってくださるのは、8代目当主の山崎嘉正社長。
信州中野から出てきた初代・山崎嘉七から、2代目、3代目と商売を広げ、3代目嘉七の時には、川越藩から御用商人として出入りを許されるまでになった。
「弘化4年(1847)には京都嵯峨御所より 「亀屋河内大掾藤原嘉永」の資格を賜り、明治維新の廃藩にいたるまで御用を勤めさせていただきました。その間に賞状、御紋付き手鏡、同じく裃と羽織、金蒔絵硯箱などをいただき、苗字、帯刀御免となったようです。 |
 |

 |
|

左手前より、亀の最中、小江戸の心、長寿落雁等、亀屋代表銘菓の数々。
 |
わたしどもは初代から代々、嘉七を襲名してきておりますが、4代目山崎嘉七(豊)を中興の祖と呼んでおります」
亀屋中興の祖と呼ばれる4代目山崎嘉七(豊)は、当時江戸で有名だった芝の『壺屋』で修行し、江戸風の、当時としてはモダンな菓子づくりを身につけて帰ってきた。店を江戸風に改めるとともに、新しい商品を揃え、菓子屋として一大革新をもたらしたという。明治維新以後は川越の経済そのものに深く関わるようになり、明治11年には第八十五国立銀行を創立、明治30年には第八十五銀行と改称、さらに川越貯蓄銀行を設立して両方の頭取を務めた。川越商業会議所(現在の商工会議所)を発足させ、初代会頭にも選ばれている。
「趣味としては絵画を好んでいたようで、菊池容斎の作品を収集し、また橋本雅邦の画宝会に率先して参画し、その多くの作品を家宝として残しています。この4代目の生誕150周年を記念して、昭和57年、本店裏に財団法人山崎美術館を設立して、所蔵の作品を一般に公開展示しました」
山崎美術館は昭和57年11月3日文化の日に開館し、その後、順調な足どりをたどり、入館者も漸増している。
「美術館を開館した頃というのは、川越が第1次の観光ブームの頃ですね。NHKで大河ドラマとして『春日局』が放映されまして、観光客の質がこの時から変わりました。川越の喜多院(星野山無量寿寺喜多院)というのは平安時代の創建とされていますが、慶長4年(1599)に徳川3代のご意見番として有名な天海が27世を継ぎ、寛永15年(1638)の火災後の再建時に、江戸城内の家光誕生の間や、春日局化粧の間を喜多院の書院、客殿として移築してきたのです。よく知られているように春日局というのは家光の乳母でしたから、大河ドラマの放映と同時に川越に観光ブームがやってきました。川越の町自体も観光宣伝につとめましたし、わたしどもでも何か観光になるものをと考えました。まあ、4代目の生誕150周年ということが大きかったわけですが、そういった考えも美術館を開館した一端にはあったわけです」
 |
|
 |

◆山崎美術館
【住所】埼玉県川越市仲町4-13
【交通】JR埼京線・東武東上線川越駅下車 徒歩20分 または市内バス仲町下車
西武新宿線本川越駅下車 徒歩10分
亀屋中興の祖、4代目山崎豊翁の生誕150年を記念して、昭和57年、本店裏に財団法人山崎美術館は設立された。 初代理事長は6代目山崎嘉七である。4代目山崎豊翁が家宝として残した橋本雅邦の作品を主として、その他に山崎家に代々伝わる町方民具を展示している。
橋本雅邦は川越藩のお抱え絵師晴園養邦の子として天保6年(1835)に江戸木挽町狩野邸内に生まれた。画道の天才と呼ばれ、13歳にして狩野勝川院雅信の門に入り、二十歳の若さで同院の塾頭となり、7つ年長の狩野芳崖とともに二神足と讃えられたという。明治22年(1889)雅邦55歳の時には創立された東京美術学校で日本画の主任教授として迎えられる。同校からは横山大観、下村観山、菱田春草などの大家が雅邦指導のもとに続出。日本近代画壇の先覚者であり、巨星であった。
 |
|

◆亀屋建物
塗り籠められた出桁、深い軒をもつ重厚な屋根など、豪華な意匠が施された外観の亀屋。建物は間口4間、奥行2.5間の店蔵と、間口2間、奥行2.5間の袖蔵を併立した袖蔵形式の蔵造りである。
【明治26年7月14日建築:市指定文化財】
 |
|

― 蔵造りの街・川越 ― 「現在、この川越の町は電信柱を地下に埋設しています。この工事が行われたのは、今から10年ほど前でしょうか。それまでは川越まつりを行う際には、山車を出そうとすると、電線や電信柱を避けて通らないといけなかったのですが、おかげでこれまで通れなかった通りも動けるようになりました。この町は片側1車線で、両側で2車線の狭い街ですけども、そうすることによって、町や道がずいぶんと広く感じられるようになりましたね」
 |

 |
|

◆あさひ銀行川越支店
【住所】埼玉県川越市幸町4
【交通】JR埼京線・東武東上線川越駅下車 徒歩20分
蔵造りと並び、川越の町を彩る大正風のレトロな建造物として有名なあさひ銀行川越支店。景観を考慮して銀行名の看板は屋上の奥に控えめに掲げてある。
大正7年(1918)、第八十五銀行本店として建てられた。昭和18年(1943)に他3行(武州銀行、忍商業銀行、飯能銀行)と合併して埼玉銀行川越支店になり、さらに平成3年に協和銀行と合併し、今日に至る。
平成8年(1996)11月、文部省の登録文化財に選出された。
 |
現在の川越の街づくりの基は長禄元年(1457)、関東管領・扇谷上杉持朝が家臣の太田道真・道灌父子に命じ、築城させてからである。 江戸時代には、江戸北辺の要衝として重要視され、 城下町として隆盛をきわめた。とくに松平伊豆守信綱の時に十か町四門前卿分の行政区画が定められ、ほぼ現在の町が形成された。 地図を広げてみると、川越の街路には「鉤の手」「丁字路」「袋小路」「七曲り」など、城下町の名残が随所にみられるのがわかる。
川越に多くの蔵造り店舗が生まれたのは、明治26年の川越大火が契機だ。この大火では町の1/3以上である1300余戸を焼失した。その復興にあたり川越の人々は、日本の伝統的な耐火建築である土蔵造りを採用したのだった。
「電信柱と電線を埋設したことによって、看板など、それまで隠れていた余計なものまで目につくようになりました。そうなるとこれはなんとかしなきゃいけないとなり、おかげで今ではあまり余計な看板などはなくなったと思います」
この蔵造りと、あさひ銀行川越支店(国の登録有形文化財)のような洋館が混在して建ち並び、小江戸情緒と大正浪漫が一体となった雰囲気のある街並みが、現在の川越の大きな魅力のひとつである。 |

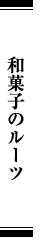 ― からくだものと点心 ― 我々が普段、店頭のケースで見かけたり、あるいは茶席で使用されたりするような現在の和菓子は、一体いつ頃から現在のような形になったのだろうか。 ― からくだものと点心 ― 我々が普段、店頭のケースで見かけたり、あるいは茶席で使用されたりするような現在の和菓子は、一体いつ頃から現在のような形になったのだろうか。
「そうですね、現在の我々が考えているお菓子というのがその完成をみるのは、やはり江戸の元禄(1688〜1704)以降のことですね」
元禄時代といえば徳川政権がもっとも安定し、俗に言う元禄文化が華開いた天下太平の時代である。すると、それ以前の和菓子というものはどのような状況におかれていたのだろう。
和菓子の歴史について山崎社長に伺った。
「もともと古代の日本では果物・木の実を総称して『くだもの』と呼んでおりまして、漢字が導入されるとそれに『菓子』の字をあてたのです。ですからお菓子というのは、自然界の果実や実のことだったのですね。そうした状況の中で、やがて遣隋使・遣唐使の時代になり、中国大陸から、穀物を主原料として加工したお菓子が伝わってきました。唐のお菓子と書いて、『からくだもの』と呼ばれたものがそれですね」
果実とは違うが、嗜好品である点が同じであるために『菓子(くだもの)』の類とされたのではないかという。
「唐菓子は仏教とともに伝わりました。それまでにも米や麦を粉にして水を加えた団子のようなものは日本にもあったようですが、唐菓子はもち米、うるち米、麦、大豆、小豆などの粉に甘味料を加えて練り、餅としたり、さらに油で揚げたりしたものだったのですね。たとえば羊羹の『羹』という字ですが、あれはもともとは『あつもの』という意味なのです。『羊』という文字がその中にありますが、元来仏教においては、肉食が禁じられていますから、穀類を餅状にして焼いたり蒸したりすることによって、いかにも羊の肉のようにしたのです。歯ごたえが肉に似ているというものが徐々に姿を変えて、唐菓子というものになったのです」
唐菓子の伝来当時は、多くは宮廷の節会や大寺、大社の供物として用いられ、庶民にはまだ縁遠い存在だったという。
「お茶の世界では、ちょっと小腹の空いたときに軽い食事をとることを点心といいます。点心というのは、ほっと一息つく、という意味なんですね。その時に必要なものがお菓子です。点心の習慣は禅宗の普及とともに鎌倉時代にはすでに広まっていたようです。唐菓子と一緒にお茶も中国から伝わってきていました。禅僧は早朝や昼食時にうどんやそうめんを食べた後に、茶の子(茶うけ)でお茶を飲んだのです。三食の習慣が始まると点心と茶の子の区別はなくなり、同義のものになりました。ですからお茶をするという習慣は平安時代からすでにありましたが、それが鎌倉・室町を経て、千利休が歴史に現れることによって、茶の作法というものが決まってきたわけです」
茶の湯によって和菓子は大きく育てられ、洗練された。
「とはいうものの、我々はすぐに現代の茶席のお菓子を想像してしまいますが、実際にはまだまだその頃は質素なものだったようです」
千利休が茶会に用いた菓子を調べてみると、麩焼(ふやき)がもっとも多く、栗、しいたけ、いりガヤ、昆布などがそれに次ぐという。麩焼(ふやき)は小麦粉を水で溶いて焼き、味噌を塗って巻くという素朴なもので、千利休のころまではこういったものを手作りにして茶席に用いることが多かったようだ。
「その理由としては、まず、砂糖というものが日本では非常に高価な物だったのです」 |

― 砂糖と南蛮菓子 ― 「砂糖が入ってくるルートとしては、まずは琉球貿易ですね。琉球から原料となるサトウキビが入ってきます。古くからの日本の砂糖の作り方は、四国の香川、徳島両県のごく限られた地域に残っておりまして、これが日本で初めて精製された砂糖といわれている和三盆(わさんぼん)です。手作りで精製されているために非常に高級な砂糖です。サトウキビをどんどん釜で焚き、それを今度は布ではさみ、糖蜜の部分だけ絞り出します。それをさらに釜で煮詰め、最後に残った白下糖(しろしたとう)という源糖を盆の上にのせて、人間の手で何度も灰汁と蜜を抜く作業(研ぎ)を何度も何度も繰り返して、結晶の小さい、口どけのよい砂糖になります。
このように原料であるサトウキビが琉球から輸入されていたものですから、日本では砂糖というものが非常に高価なものでした。今でも疲れた時には甘いものが欲しくなりますが、当時としては、栄養価も高く、薬の代用品のような扱いだったのです。ですから庶民の口にはなかなか入らないものでした。種子島に鉄砲が伝来してヨーロッパとの交易が始まるころまではほとんど食用にもされていなかったわけです」
南蛮菓子とよばれる菓子類が日本に入ってきたのは、室町末期あたりからのポルトガル人をはじめとするヨーロッパ人との接触によるものである。当時はまだほとんど食用とされなかった卵や砂糖を多く使い、宣教師たちが布教に盛んに利用したため、急速に普及したという。カステラ、ボーロ、ビスケット、金平糖などである。

― 元禄に華開いて ― 「江戸期になり、天下太平となるとともに、茶の湯、お茶の世界というものが浸透していき、それが一気に華開いたのが元禄時代です。お菓子だけではなく、衣装からなにからさまざまなものが文化として成熟し、本当にいいものが作られるようになりました。基本的に日本の文化というものは関西・京都からきています。お菓子もやはりそうです。京菓子からきています。よくたいした価値のないものを『くだらないもの』と言いますが、これは当時のことからきた言葉です。当時の文化というものは関西・京都から江戸へ『下って』いくのですが、ただその時にも江戸において受け入れられないもの、普及しないものがあります。その時に江戸で歓迎されないようなものはたいしたものではない、つまり『下っていかない』転じて『くだらないもの』といわれるようになったのです。 京都は文化の発信地であり、江戸は最大の消費地ですからね。また江戸には数々の大名屋敷がありますから、江戸のお菓子屋さんがその大名屋敷に納めるために、京都の京風菓子のノウハウをどんどん取り入れていったのです。同時に京都からは三越、大阪からは大丸というように、呉服屋さんなども江戸に出てくるようになります。そういった文化背景や、砂糖生産の急増という技術的進歩があって、現在我々がみているような茶席の生菓子というものが、元禄の頃、完成したのです」
太平の世による商業の発展、経済成長は菓子屋の規模自体を大きくし、江戸末期にはさらに多様な和菓子が出揃うようになったという。
「とはいうものの、そういった菓子を手にすることができたのは、あくまでも上流社会の話です。一般庶民の口に入るのはまだ麦芽糖を使った飴であるとか、団子などです。砂糖はまだまだ高級なものであることにはかわりなかったですから。当時というのは砂糖をふんだんに使えば使うほど高級であるという価値観です。お菓子というものはたいへんな金額でもって御用商人が大名などに納めたものだったのです。ですから菓子というものは、口に入れた時の味もそうですけれども、使い方としては大名同士などでの進物用としての価値が高かったのです。味以前にまず高級品であり、そういった高級品を相手に差し上げることによって、いかに敬意を表すかとというところに重きが置かれていたのです。ですから昔の菓子の見本帳など見ますと、現代のものよりも大きくて、さらに手がこんでいますね」
|

 |
 |

山崎家(亀屋本店)に残されている昔の菓子の製法書。(山崎美術館内に展示)
 |
|
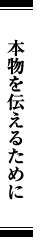 ― 稼業は世の進歩に順ずべし ― ― 稼業は世の進歩に順ずべし ―
「甘ければ甘いほど良いお菓子という評価は、おそらく昭和40年くらいまではそうだったのではないかと思います。砂糖の生産量や価値ではなく、時代の価値観の違いですね。昭和40年代くらいから菓子はその甘さを抑えるようになったのです。ひとつには生活の中で人間が体を動かすことが少なくなってきたということ。洗濯、掃除などそれらも昔よりは体を使わない。労働が少なくなると、甘い物への欲求が少なくなります。また、精神的にも魅力が減ってきた。茶の湯でいう点心、ちょっと心をひとつ休ませる、そういう生活のゆとりができて、経済的にも甘い物を生活の中にどんどん取り入れることができるようになった。それが時代が進むにつれて、甘い物に対する魅力を逆に薄れさせていったのではないでしょうか。甘い物だけではなく、現代では味が全体的に薄味傾向、ぼんやりとした傾向にあるように思いますね」
昭和50年代あたりから日本人の味覚自体が変わってきたのではないか、と山崎社長はいう。
「亀屋の家訓に『稼業は世の進歩に順ずべし』、つまり世の進歩に着目しながら、変えていかなくてはならないというものがあります。伝統には変えてはいけない部分と革新していく部分の両方があり、メリハリをつけていくことが大切だと思います。時代の流れに合わせて作り方を変え、配合も変え、味も変え、お菓子自体を変えていく必要があります。たとえば餡というものは、昔は甘ければ甘いほど良い餡だったのですが、現在は違います。そうすると原料の使い方によって商品の味が決まってきます。砂糖ひとつとっても、グラニュー糖から三温糖、ザラメのたぐいであるとか、ごく普通の上白糖であるとか、いろいろ砂糖もあります。いい砂糖を使うことによって、使う小豆も変わります。また、いい小豆に上白糖を使ってしまうと小豆の良さというものがダメになってしまいます。砂糖にも小豆にもアクがあります。今は良い小豆であればその風味が口の中に、また鼻に抜ける、ということをきちっと感じさせるような餡にしなくてはなりません。そのためには小豆だけ良くてもだめだし、砂糖だけでもだめで、釜もいいものを使わなくてはならないのです。普通の鉄の釜やアルミの釜ではなくて、銅の釜が必要です。銅という素材は熱の伝わり方が柔らかくて、全体にまんべんなく伝わります。そして小豆にはアクがありますから、アク抜きをしっかりして、風味が出るように作るのです。こうすることによってただ甘いだけではなく、現代風の甘みがそれでようやく引き出せます。しかし、それと同時に守らなくてはならない大切なことがあります。それは現代風にアレンジすると同時に本物の味というものをきちんと伝えていかなくてはならない、ということです」 |

― 大福はかたくなるもの ― 高度成長時代、味の追求よりも出店であるとか、会社の規模を大きくすることに目がいっていた時期があったという。効率と経済性が優先し、菓子を買う客の考えていなかった、と山崎社長は当時を思い出すように語る。
「優先順位を間違えていたわけです。まずはお客様のことを考えなくてはいけないのに、出店をどう増やすかを考えていた時期がありました。ですから今はまずお客様のことを考え、お客様のためにどういう商品を作るかを考えています。たとえば大福餅というものは、和菓子屋の世界では作った翌日には固くならなくてはいけないのです。しかし大手のメーカーさんなどが作ってる大福餅はわたしどもの半分の値段で、一週間たっても柔らかいのです。そういうものを子供に一度食べさせると、子供の頃の味覚の記憶っていうのは強烈なものがありますから、そうすると一週間たっても柔らかい大福餅が、これが本物の大福餅だと思ってしまいます。むしろ我々のように本物の餅を使って、翌日になったらちゃんと固くなるような大福餅は、クレームの対象になるのです。固くなった大福餅は焼いて召し上がっていただければよいのですが、そういうことを今は知らないお客様もいらっしゃいます。生活の様式が変わったということもあるし、固くなった餅を焼いたりふかし直したりということを、我々も伝えてこなかったわけです。ようはいかに消費者に対して手となり足となり親切丁寧に物を売っていくか、ということを置き忘れていたわけです」
この本物の大福餅を売り出すにあたり、亀屋では販売員の再教育をしたという。ほかの大福とは違う昔ながらの大福餅で、時間がたつと固くなること、固くなった場合は焼いて召し上がっていただくことなど、適切な説明ができるようにした。すると的確な説明ができる販売員がいる売場では、それがきちんと売上数字に表れてきたという。
「そういう意味ではなくしてしまったものを、常に継承していくという、まあこれは食べ物だけではなくて、文化も含んでこれからまた伝えて行くという使命があると思っています。お菓子を通して、日本人の心だとか生活だとかを伝えていかないと、将来の和菓子の業界というのは非常に厳しい状態になります。本物を守り伝えつつ、革新をめざしていく。『稼業は世の進歩に順ずべし』という家訓を守り、次世代へと伝えていきたいと思います」 |

 |

亀屋8代目当主・山崎嘉正社長
本社/埼玉県川越市仲町4-3
TEL:049-222-2051
|
|
|

